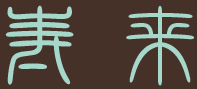| >>
一.
(株)豊臣商事は、大阪を本拠として、全国に7つの支社と24の事業所を持つ総合商社である。
傘下には200を超える子会社、関連会社が名を連ね、実に様々な分野で営業活動を行っている。日本有数の大企業である。
本社は、大阪キタの高層ビル街の中にある。地下2階・地上35階建ての自社ビルは、元々は豊臣商事のものではなかったのだが、立地を気に入った社長が所有者の会社ごとビルを買収して本社に作り変えた。買収された元所有者の会社はといえば、今は豊臣商事の子会社となって、そのビルの中腹部分で不動産業を営んでいる。
その日、豊臣商事本社ビルでは、半期に一度の定例会議が行われていた。
定例会議といっても、その規模は大きい。グループ傘下の主要会社役員が全国から集まり、一堂に会するのだ。
秘書室長として社長の背後の采配をふるう三成にとって、この定例会議の日は、半年で一番気を使う日だった。
−6:00PM−
会議終了から、約二時間。
会議後の諸々の段取り、雑務の指示を終えた三成は、付箋のついた書類とディスクの束を室長補佐の島に手渡した。
「これを各部署に下ろしておいてくれ。今日の会議の資料の取り纏めと議事録だ。
…社長はもう会場に着かれたか?」
「ええ、20分ほど前にね。
それにしても室長の仕事はいつも迅速ですな。もう先程の取り纏めが下ろせる状態になったとは」
すると三成はふんと顔を逸らした。
「事前にある程度まとめておけば、それほど手間はかからん。それより島、俺は今日はこれで帰る。後のことは頼んだぞ」
「はいはい、わかってますよ。定例会議の日だけは室長、死んでも残業しませんもんね。…いい加減、口を割ったらどうですか?」
どこの社のお嬢さんと、逢引きしてるんです?――
からかうように言った島に、三成は鋭い視線を向けた。本気ではないが、なまじ整っている顔をしているだけに、切り込むような迫力がある。島は怖い怖いとおどけて、肩をすくめた。
時折ふざけて絡んでくるが、この男は公私をきっちり分けて、やるべき事は要領よく完璧にこなせる奴だ。
後は彼に任せておけばいい――三成はお先に、と滅多に使わない言葉を残し、秘書室を後にした。
二.
逢引きをしている、確かに。
それも女とじゃなく、男と。
普通じゃない。そうだ。わかってる。
でも仕方がない。
出会って、どうしようもなく惹かれて、止めることができなかった。
何がそんなに自分の心を突き動かしたのか。
心でなく、体でなく。もっと奥の、そう魂そのものが強烈に彼に惹きつけられた理由を。
俺は未だに、見つけられずにいる――
秘書室を出た三成は、静まり返った34階の廊下を一人で歩いていた。
最上階の真下に当たるこのフロアには、昼間会議が行われていた大会議室のほかに、待機部屋と呼ばれる応接室が数部屋ある。
数時間前まで人であふれていた大会議室の前を通り、三成は一番端の応接室のドアを開けた。
――まだか…
無人の室内、正面の大きな窓からは、藤色の空に輝く一番星が見えていた。
夕闇が色を深めていくこの時間の空は、言い様がなく美しい。三成はソファではなく、腰高のはめ込み窓に浅く腰掛けると、窓枠に寄り掛かり、外を眺めた。
街には夜が訪れようとしていた。
林立するビルに、ぽつぽつと明かりが灯り、
その合間を縫って伸びる高速道路を、テールランプの赤が彩る。
次第に増えていく光の粒を見ながら、三成はひどく満ち足りた想いに胸が温まるのを感じた。
しばらくして、軽快なノックの音と共にようやく待ち人が入ってきた。
「兼…」
呼びかけた三成の声が、途中で止まる。
相手は携帯で会話をしている最中だった。
すらりとした長身に、濃いグレーの細身のスーツ。ストレートの黒髪と、きつくはないが芯の強そうな端整な容貌。それを際立たせるシンプルな眼鏡。
一見して、役職に就いている人間だ。独特の空気を纏っている。
彼は、直江兼続――東京支社で唯一人、支社長秘書を務める男だった。
兼続は、よく通る闊達な声で話をしながら、机の上に大きな革鞄を置くと、三成にちらりと目配せをした。
”すまんな――”といったところだろう。
彼のマイペースはいつものことで、もう慣れている。
三成は”気にするな”と手をひらひらさせると、また窓の外へと顔を向けた。
「…そうか、わかった。ではその件は私から支社長に伝えておこう。それで…」
話している間も、絶えずごそごそと物音が止まらない。三成は、相変わらず騒がしい奴だと軽いため息をついた。
夜景をバックに、携帯を肩で押さえて話を続ける兼続が、窓に映っている。
彼の手元には、いつの間にかノートパソコンとファイルが二冊開いていた。パラパラとページをめくる手が、止まってはマウスへ。止まってはファイルへと往復を繰り返している。
しばらくすると、今度は手帳とおぼしき冊子を取り出した。
「…そうだな、一週間後。…ん。……ん…」
忙しく手を動かしながら、それでも澱みなく会話を続ける兼続を見て、いつもながらタフな奴だと三成は感心した。
彼の在籍する東京支社は、ここ本社に次いで取引先が多い。部下を持たず、一人で支社長の補佐を務める彼の仕事量は、三成より多いかもしれなかった。
しかし彼の表情はいたって普通で、翳りがない。
実に平然としているのだ――多少騒がしくはあるが。
「…ははは。その件はよろしく。では――」
ピ…と携帯の終話音が聞こえ、ようやく三成は兼続の方へと顔を向けた。
二つ折りにした携帯をポケットにしまう兼続の手元には、もう何一つ出ていなかった。書類もパソコンも…。
一つの作業を終えるときには、もう次の作業に取り掛かれるようになっている。
彼は常に、そういう仕事をしている。
「相変わらずせわしいな、兼続」
口調は皮肉めいていても、三成の気持ちは褒めている。
「はは、そうだな」
それをわかっている兼続は、あっさりと笑って受け流した。
こいつのこういうところが居心地良い――三成はふっと笑って話題を変えた。
「上杉支社長はもう行ったのか?」
「ああ、さっきな」
次々と増えるグループ会社の連携を保つため、定例会議の後には必ず社長クラスでの懇親会が行われる。
兼続の上司である上杉景勝も当然、出席を命じられていた。
宴会は好きではない。特に豊臣社長の主催する派手派手しい宴会は大の苦手だ、という景勝だが、こればかりはどうしようもない。渋い顔をさらに渋くして車に乗り込んだ景勝を、ニッコリと見送って兼続はここへ来たのだった。
今日はこれで仕舞いだ――そう言って、兼続はかっちりと締めたネクタイの首元をしゅっと弛めた。ふー、と息をついたその表情が和らいだのに気付き、三成はお疲れと笑い掛けた。
三.
「…大阪の夜景も、東京とあまり変わらないな」
窓辺に腰掛ける三成に近寄り、兼続が外を眺めてぽつりと言った。
「目に刺さるほど光が多くて……胸が痛くなる」
その声が少し沈んでいるように感じて三成が思わず顔を上げると、兼続はやや疲れたような…苦しげにも見える表情を浮かべていた。
こいつのこんな顔は初めて見る――そんなことを思いながら、三成は何気なく口を開いた。
「…そうか?俺は好きだがな」
言って、三成も窓の外へと視線を移した。
夜に包まれ輪郭の消えた街で、光は静かに強く、そして無数に輝いていた。
「あの光を見ていると、俺は不思議と心が落ち着く」
そう言う三成の口調が、常になく優しく聞こえて、
「みつなり…?」
兼続が三成を見た。
街の灯を映した三成の瞳が、それは穏やかな、やわらかい光を宿していた。
「あの光の元には、沢山の人がいる。
色んな思いや希望を抱えて、
自分のため、誰かのため、
…未来のために。
今を懸命に生きてるんだろう――
それを思うと、何やら嬉しいような温かいような…不思議な気分になってな」
感傷的で、俺らしくないだろ?笑ってくれていいぞ――
そう言って苦笑した三成を、兼続は穴が開くほどまじまじ見つめた後、ありったけの力を込めて抱き締めた。
「笑うか馬鹿者――」
何だ突然、痛い、放せと怒る三成の声は、兼続の耳にはほとんど入っていなかった。
『戦のない世の中を』
『人々が笑って暮らせる世を』
四百年の昔、自分達はその切なる思いを胸に戦った。
三成にその記憶はない。
しかし――
「そうだな。あの光は人が生きている証しだ。
何千、何万という人々が、明日を約束されて生きている――」
だからおまえの心は安らぐのか。
人々が安寧に暮らせる世、それを誰より望んでいたのは、おまえだったから――
転生の輪に記憶を消されてしまっても。
彼は変わってなどいない。何一つ。
――だから私達は出会い、惹かれ合った。
「――出ようか、三成」
抱き締める腕をゆるめて、兼続が三成の顔をのぞき込んだ。すると三成は、心底意外そうに眉を上げた。
「珍しい…いつもはなし崩しに襲ってくるくせに。一体どういう風の吹き回しだ?」
兼続はなし崩しとは失礼だとぼやくと、掛けていた眼鏡をはずし、普段あまりしない、軽くて優しいキスをした。
「いや、いろいろと――話をしたくなってな」
「なんだ今更改めて…気味が悪いぞ」
「………。
どこかいい店を知らないか?静かで、ゆっくり話せて」
「夜景が見える、か?」
「そう」
街の灯りが、ひどく切なく映るのは。
戦のない世を望んで戦い、志半ばで斃れたおまえを、私が忘れられないからだ。
もぎ取られるようにして突然喪った心の半分が、気が狂いそうなほど痛くて。
…痛くて、心残りで。
だから私は前世の記憶をひきずったまま、この世に生まれた。
「…うってつけの場所がある」
するっと兼続の腕を抜け出し、三成が言った。
「む…どこだ?歩いて行ける店か?」
「店じゃない。いいから来い」
おね…社長婦人がこの前教えてくれた。あそこからなら360度の夜景が臨めて、あまつさえ夜空まで見える――
三成は内ポケットから鍵を一つ取り出すと、兼続の方へポイと放った。
もっとも、呑むつもりなら酒は買って行かねばならんがな。
おまけに吹きっ晒しだぞ――
それでもいいか?と訊く三成に、兼続は笑って無論と答えた。
「社屋の屋上なら、閉店もないしな」
話をしよう。
積もる話を。
――ここで私達がこうしているのには、
きっと沢山の理由があるはずだから――
人工の灯が照らしだす仄暗い夜空に、月が輝いていた。
遠い昔と変わらぬ優しい光で、地上の二人を見守るように。
(株)豊臣商事は、大阪を本拠として、全国に7つの支社と24の事業所を持つ総合商社である。
傘下には200を超える子会社、関連会社が名を連ね、実に様々な分野で営業活動を行っている。日本有数の大企業である。
本社は、大阪キタの高層ビル街の中にある。地下2階・地上35階建ての自社ビルは、元々は豊臣商事のものではなかったのだが、立地を気に入った社長が所有者の会社ごとビルを買収して本社に作り変えた。買収された元所有者の会社はといえば、今は豊臣商事の子会社となって、そのビルの中腹部分で不動産業を営んでいる。
その日、豊臣商事本社ビルでは、半期に一度の定例会議が行われていた。
定例会議といっても、その規模は大きい。グループ傘下の主要会社役員が全国から集まり、一堂に会するのだ。
秘書室長として社長の背後の采配をふるう三成にとって、この定例会議の日は、半年で一番気を使う日だった。
−6:00PM−
会議終了から、約二時間。
会議後の諸々の段取り、雑務の指示を終えた三成は、付箋のついた書類とディスクの束を室長補佐の島に手渡した。
「これを各部署に下ろしておいてくれ。今日の会議の資料の取り纏めと議事録だ。
…社長はもう会場に着かれたか?」
「ええ、20分ほど前にね。
それにしても室長の仕事はいつも迅速ですな。もう先程の取り纏めが下ろせる状態になったとは」
すると三成はふんと顔を逸らした。
「事前にある程度まとめておけば、それほど手間はかからん。それより島、俺は今日はこれで帰る。後のことは頼んだぞ」
「はいはい、わかってますよ。定例会議の日だけは室長、死んでも残業しませんもんね。…いい加減、口を割ったらどうですか?」
どこの社のお嬢さんと、逢引きしてるんです?――
からかうように言った島に、三成は鋭い視線を向けた。本気ではないが、なまじ整っている顔をしているだけに、切り込むような迫力がある。島は怖い怖いとおどけて、肩をすくめた。
時折ふざけて絡んでくるが、この男は公私をきっちり分けて、やるべき事は要領よく完璧にこなせる奴だ。
後は彼に任せておけばいい――三成はお先に、と滅多に使わない言葉を残し、秘書室を後にした。
二.
逢引きをしている、確かに。
それも女とじゃなく、男と。
普通じゃない。そうだ。わかってる。
でも仕方がない。
出会って、どうしようもなく惹かれて、止めることができなかった。
何がそんなに自分の心を突き動かしたのか。
心でなく、体でなく。もっと奥の、そう魂そのものが強烈に彼に惹きつけられた理由を。
俺は未だに、見つけられずにいる――
秘書室を出た三成は、静まり返った34階の廊下を一人で歩いていた。
最上階の真下に当たるこのフロアには、昼間会議が行われていた大会議室のほかに、待機部屋と呼ばれる応接室が数部屋ある。
数時間前まで人であふれていた大会議室の前を通り、三成は一番端の応接室のドアを開けた。
――まだか…
無人の室内、正面の大きな窓からは、藤色の空に輝く一番星が見えていた。
夕闇が色を深めていくこの時間の空は、言い様がなく美しい。三成はソファではなく、腰高のはめ込み窓に浅く腰掛けると、窓枠に寄り掛かり、外を眺めた。
街には夜が訪れようとしていた。
林立するビルに、ぽつぽつと明かりが灯り、
その合間を縫って伸びる高速道路を、テールランプの赤が彩る。
次第に増えていく光の粒を見ながら、三成はひどく満ち足りた想いに胸が温まるのを感じた。
しばらくして、軽快なノックの音と共にようやく待ち人が入ってきた。
「兼…」
呼びかけた三成の声が、途中で止まる。
相手は携帯で会話をしている最中だった。
すらりとした長身に、濃いグレーの細身のスーツ。ストレートの黒髪と、きつくはないが芯の強そうな端整な容貌。それを際立たせるシンプルな眼鏡。
一見して、役職に就いている人間だ。独特の空気を纏っている。
彼は、直江兼続――東京支社で唯一人、支社長秘書を務める男だった。
兼続は、よく通る闊達な声で話をしながら、机の上に大きな革鞄を置くと、三成にちらりと目配せをした。
”すまんな――”といったところだろう。
彼のマイペースはいつものことで、もう慣れている。
三成は”気にするな”と手をひらひらさせると、また窓の外へと顔を向けた。
「…そうか、わかった。ではその件は私から支社長に伝えておこう。それで…」
話している間も、絶えずごそごそと物音が止まらない。三成は、相変わらず騒がしい奴だと軽いため息をついた。
夜景をバックに、携帯を肩で押さえて話を続ける兼続が、窓に映っている。
彼の手元には、いつの間にかノートパソコンとファイルが二冊開いていた。パラパラとページをめくる手が、止まってはマウスへ。止まってはファイルへと往復を繰り返している。
しばらくすると、今度は手帳とおぼしき冊子を取り出した。
「…そうだな、一週間後。…ん。……ん…」
忙しく手を動かしながら、それでも澱みなく会話を続ける兼続を見て、いつもながらタフな奴だと三成は感心した。
彼の在籍する東京支社は、ここ本社に次いで取引先が多い。部下を持たず、一人で支社長の補佐を務める彼の仕事量は、三成より多いかもしれなかった。
しかし彼の表情はいたって普通で、翳りがない。
実に平然としているのだ――多少騒がしくはあるが。
「…ははは。その件はよろしく。では――」
ピ…と携帯の終話音が聞こえ、ようやく三成は兼続の方へと顔を向けた。
二つ折りにした携帯をポケットにしまう兼続の手元には、もう何一つ出ていなかった。書類もパソコンも…。
一つの作業を終えるときには、もう次の作業に取り掛かれるようになっている。
彼は常に、そういう仕事をしている。
「相変わらずせわしいな、兼続」
口調は皮肉めいていても、三成の気持ちは褒めている。
「はは、そうだな」
それをわかっている兼続は、あっさりと笑って受け流した。
こいつのこういうところが居心地良い――三成はふっと笑って話題を変えた。
「上杉支社長はもう行ったのか?」
「ああ、さっきな」
次々と増えるグループ会社の連携を保つため、定例会議の後には必ず社長クラスでの懇親会が行われる。
兼続の上司である上杉景勝も当然、出席を命じられていた。
宴会は好きではない。特に豊臣社長の主催する派手派手しい宴会は大の苦手だ、という景勝だが、こればかりはどうしようもない。渋い顔をさらに渋くして車に乗り込んだ景勝を、ニッコリと見送って兼続はここへ来たのだった。
今日はこれで仕舞いだ――そう言って、兼続はかっちりと締めたネクタイの首元をしゅっと弛めた。ふー、と息をついたその表情が和らいだのに気付き、三成はお疲れと笑い掛けた。
三.
「…大阪の夜景も、東京とあまり変わらないな」
窓辺に腰掛ける三成に近寄り、兼続が外を眺めてぽつりと言った。
「目に刺さるほど光が多くて……胸が痛くなる」
その声が少し沈んでいるように感じて三成が思わず顔を上げると、兼続はやや疲れたような…苦しげにも見える表情を浮かべていた。
こいつのこんな顔は初めて見る――そんなことを思いながら、三成は何気なく口を開いた。
「…そうか?俺は好きだがな」
言って、三成も窓の外へと視線を移した。
夜に包まれ輪郭の消えた街で、光は静かに強く、そして無数に輝いていた。
「あの光を見ていると、俺は不思議と心が落ち着く」
そう言う三成の口調が、常になく優しく聞こえて、
「みつなり…?」
兼続が三成を見た。
街の灯を映した三成の瞳が、それは穏やかな、やわらかい光を宿していた。
「あの光の元には、沢山の人がいる。
色んな思いや希望を抱えて、
自分のため、誰かのため、
…未来のために。
今を懸命に生きてるんだろう――
それを思うと、何やら嬉しいような温かいような…不思議な気分になってな」
感傷的で、俺らしくないだろ?笑ってくれていいぞ――
そう言って苦笑した三成を、兼続は穴が開くほどまじまじ見つめた後、ありったけの力を込めて抱き締めた。
「笑うか馬鹿者――」
何だ突然、痛い、放せと怒る三成の声は、兼続の耳にはほとんど入っていなかった。
『戦のない世の中を』
『人々が笑って暮らせる世を』
四百年の昔、自分達はその切なる思いを胸に戦った。
三成にその記憶はない。
しかし――
「そうだな。あの光は人が生きている証しだ。
何千、何万という人々が、明日を約束されて生きている――」
だからおまえの心は安らぐのか。
人々が安寧に暮らせる世、それを誰より望んでいたのは、おまえだったから――
転生の輪に記憶を消されてしまっても。
彼は変わってなどいない。何一つ。
――だから私達は出会い、惹かれ合った。
「――出ようか、三成」
抱き締める腕をゆるめて、兼続が三成の顔をのぞき込んだ。すると三成は、心底意外そうに眉を上げた。
「珍しい…いつもはなし崩しに襲ってくるくせに。一体どういう風の吹き回しだ?」
兼続はなし崩しとは失礼だとぼやくと、掛けていた眼鏡をはずし、普段あまりしない、軽くて優しいキスをした。
「いや、いろいろと――話をしたくなってな」
「なんだ今更改めて…気味が悪いぞ」
「………。
どこかいい店を知らないか?静かで、ゆっくり話せて」
「夜景が見える、か?」
「そう」
街の灯りが、ひどく切なく映るのは。
戦のない世を望んで戦い、志半ばで斃れたおまえを、私が忘れられないからだ。
もぎ取られるようにして突然喪った心の半分が、気が狂いそうなほど痛くて。
…痛くて、心残りで。
だから私は前世の記憶をひきずったまま、この世に生まれた。
「…うってつけの場所がある」
するっと兼続の腕を抜け出し、三成が言った。
「む…どこだ?歩いて行ける店か?」
「店じゃない。いいから来い」
おね…社長婦人がこの前教えてくれた。あそこからなら360度の夜景が臨めて、あまつさえ夜空まで見える――
三成は内ポケットから鍵を一つ取り出すと、兼続の方へポイと放った。
もっとも、呑むつもりなら酒は買って行かねばならんがな。
おまけに吹きっ晒しだぞ――
それでもいいか?と訊く三成に、兼続は笑って無論と答えた。
「社屋の屋上なら、閉店もないしな」
話をしよう。
積もる話を。
――ここで私達がこうしているのには、
きっと沢山の理由があるはずだから――
人工の灯が照らしだす仄暗い夜空に、月が輝いていた。
遠い昔と変わらぬ優しい光で、地上の二人を見守るように。